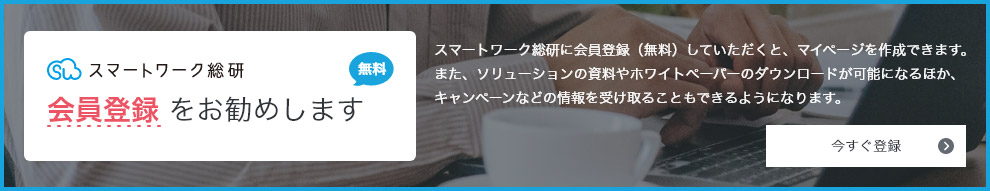大澤正彦

https://osawa-lab.com/

「ドラえもんをつくる」ための3つの道筋
――最初に大澤先生の現在の研究テーマについてご説明いただけないでしょうか。
大澤「ドラえもんをつくる」ことが僕のメインテーマです。大澤研究室では、3つのチームに分かれて研究を進めています。
1つ目のチームが「インテリジェンスチーム」です。ドラえもんの知性の部分をつくっています。最近のAIの急成長はディープラーニングといわれる技術の成功に起因しています。ディープラーニングには、「画像を認識することに特化したもの」や、「言葉を認識することに特化したもの」などがあり、基本的な技術が用途に応じて作り込まれています。我々が研究しているのは「人の心を学ぶことに特化したディープラーニング」です。画像を学んだり、言語を学ぶのと同じように、心を学ぶことができると考えています。人の心にはこういう性質があると思うから、こういうディープラーニングの技術をつくったらいいよねといったような議論をしています。
2つ目は、「インタラクションチーム」と呼んでいるのですが、人とロボットの関係性を考える研究を進めるチームです。ロボットがどう振る舞ったら人と関わりやすいのかや、ロボットが人を助けるだけではなく、むしろ人に助けてもらえるロボットはどうつくればいいのかといったことです。代表的な研究としては、ドラえもんに実際に出てくる「ミニドラ」のようなロボットをつくるというプロジェクトがあります。ミニドラは、「ドラドラ」とか「ドララ」といった言葉しかしゃべらないロボットですが、それでも人とうまく関わることができるんです。そのロボットに何ができるか考えたり、人とロボットの関係性を研究することで得られた成果は、ドラえもんづくりのロードマップにつながると信じています。
最後に3つ目は、ソーシャル・インプリメンテーション(社会実装)の意味で「インプリメンテーションチーム」と言っています。未来のことばかり考えて、今すぐに役に立たないものを研究しても、求心力がなく研究資金や人が集まらなくて困ってしまう。だから、今役に立つことをやろうと。僕は本当にドラえもんをつくるところまでたどり着く気でやっているので、開発した技術がちゃんと役に立つことを示し、これが世の中を良くしていくだろうという納得感を社会から得ることを目標としたチームです。ロボットを使ってものを売ったり、すぐに使える人工知能やエージェントの技術開発をしたりしています。

日本大学のほか専修大学でも授業を持ち、約50人の学生を指導している大澤先生。
コミュニティがベースになった研究組織
――大澤先生がセンター長を務められている、次世代社会研究センター(RINGS)はどういう組織ですか。
大澤 次世代社会研究センター(RINGS)は、簡単に言えば、産官学連携で、しかも文理融合で、新しい価値を生み出していこうとする研究センターです。助教になる前から構想していて、2020年12月に立ち上げました。
RINGS(https://chs.nihon-u.ac.jp/research/rings/)の特徴は、プロジェクトをベースにするのではなく、コミュニティをベースにしていることです。産官学連携のプロジェクトの多くは、トップダウンで「このプロジェクトをやりなさい」、「このプロジェクトで人を集めなさい」と言って、連携することが目標になっているところがあると思うんです。僕が目指しているのは、仲間同士がつながっているというコミュニティが最初にあって、その中で一緒に研究したら面白いよねという、プロジェクトがあとから出てくるような形をつくりたいと思っています。そこが既存の組織と大きく違うところです。
「100人で100人の夢を叶える」をビジョンとして掲げています。研究者を目指す人や、研究者のなかにも、苦しい思いをしている人がたくさんいるんです。たとえば、頭も良く優秀なのに全然お金がもらえないとか、安定した職につけないとか、教授とうまくいかなくなって研究が続けられないとか、そういう人たちを見てきました。そこで、既存の価値軸に縛られずに、その人が追い求めたい、こうありたいと思うものをありのまま生かせるような場所、そういう研究組織をつくりたいとずっと強く思ってきたんです。
これまでの組織では既存の価値軸に合わせて、わかりやすいように生きざるを得なかった。会社で言えば、組織の目標があって、その目標に対して、100人の組織なら100人それぞれに仕事が割り当てられてしまう。そうではなくて、1人のやりたいことをみんなで尊重して、100人で支え合う。100人いたら、やりたいことが100通りあるような、そういう関係性をめざせないだろうかと。1人1人がありたい形、やりたいことを本気で追求していく。その総和として、今の価値創出のあり方を超えていく。そんな究極的な未来を思い描いてやっています。もちろんやりたいことの1つには、僕の「ドラえもんをつくる」という夢があって、僕がドラえもんをつくることでみんなのことも応援するし、みんなが活動することで僕のドラえもんづくりを応援してもらえるような、そういう関係性をめざしたいと思っています。
――次世代社会研究センター構想のルーツになっているのが、大澤先生が大学生のときに立ち上げた「全脳アーキテクチャ若手の会(https://wbawakate.jp/)」だと思いますが、その経緯はどんなことだったのでしょうか。
大澤 もともと、当時富士通研究所におられた山川宏先生や、東京大学の松尾豊先生などがやっていた「全脳アーキテクチャ勉強会(https://wba-initiative.org/events/wba_seminars/)」という人工知能について研究する人たちが交流する勉強会があって、学部生として参加していました。参加者が200〜300名程度いたのですが、終わったらみんな早々と解散してしまう。僕が21才のときだったと思うのですが、そのまま帰ってしまうのはもったいないなと、そこに参加していた若い人たちとつながったら面白いだろうなと感じていました。
それで、若い人たちだけで交流しようという「若手の会」を始めたのです。でも、やり始めたら、その取り組みを面白いと思ったシニアの人たちも参加してくれたので、若手だけの組織でもなくなりました。また当初は人工知能の勉強会として始めたのですが、神経科学の人も、心理学の人も参加してくれて、会計が専門の人やダンスの先生とか、そういう人まで参加して、どんどん広がって、結果的にオープンなコミュニティと評価していただけました。その過程でオープンに研究することの価値をすごく感じました。だからこそ「オープンである」という自分たちのあり方を、結果論としても、戦略としても位置づけられたと思います。
オープンに研究することは社会的には評価されますが、研究者コミュニティのなかでは、必ずしもそうではありません。クローズドで研究が行われているのは、クローズドであるべき理由とか、そのほうが都合が良い理由がたくさんあるわけです。自分たちの知見を他人に取られてしまったら成果として認められないこともあるかもしれません。専門領域が違う人から様々な指摘を受けて、自分が立てた仮説から論点がズレていってしまうかもしれないし、外に出ている暇があったら1分1秒でも長く研究して成果を出した方がいいという考え方も間違いではないと思います。
だから、クローズドで研究するデメリットを克服したわけではないですし、いつでも研究はオープンにすべきだ、と主張しているわけでもありません。でも、やってみたからこそわかったメリットもやっぱり出てきています。「そのほうがいいですよ」といつもおすすめするわけではないですが、僕らがみんなと違う方向で研究に向き合っているから、「こういう良さ、こういうメリットが見えましたよね。だからもっといいやり方を模索できるんじゃないでしょうか」ということは言えるのかなと。われながら謙虚に思っていますね(笑)。
僕はたまに、RINGSってドラえもんなんじゃないかと思うんです。「ドラえもん」の話は、のび太くんがジャイアンにいじめられて、「ドラえもん! なんとかして」と助けを求めると、思いもよらない解決策が提案されるというところから始まりますが、助けを求めるところが、一番重要なところじゃないかと思います。今の世の中は、困ったことがあるときに誰にも相談できないし、解決策の目途が立たないとどうしようもないみたいな状況になって、塞ぎ込んでしまう人もいっぱいいると思うんです。でもそんなとき、とりあえず「ドラえもん! なんとかして」と言える場所があったらかなり幸せだなと。それを組織という集団で、それぞれが余裕があるときに、ちょっとずつドラえもんになってあげるみたいな、そういうみんなの集合体としてのドラえもん的存在が組織としてできたら、きっとそれはすばらしいものだろうし、今、必要とされているものだと思います。
支え合いながら生きていく「ウニ型組織」
――大澤先生は、「ウニ型組織」という提案もされていますが、これはRINGSのことですか。
大澤 そうですね。「全脳アーキテクチャ若手の会」をやっていたときに生まれた言葉で、「大澤は、どんな組織をつくりたいの?」と言われて、パッと出た答えが「ウニみたいな組織をつくりたい」と。「えっ?」と言われたんですけど、そんなに的を外していないと思っているので、今も言っています。ウニのとげのように、みんながばらばらの方向を向いていていい。ばらばらの方向を向いているけれども、根っこでしっかりつながっていて、誰かが進むときにはそっちの方向にみんなで協力して動く。どのトゲが優秀とか、どのトゲがすごいとかではなくて、大きくても小さくても、それが全体として美しいわけです。そして、中にすごくおいしいものが詰まっている。そういう組織はほんとにいい気がするなと思って。そんな組織のあり方はないだろうかと言っていたら、共同研究者が学会で「ウニ型組織とは?」という研究発表をしてくれました。
RINGSには、学生もいれば、メディアの編集長やアナウンサー、科学館のサイエンスコミュニケータ、研究者、IT企業の社員などが参加しています。立場も、評価のされ方もまったく違う人たちが集まって、お互いを認め合って、私たち、こんなふうになりたいという話をしているのは、すごくいいと思っています。
別の言葉で言うならば、「新しい村」の形をつくりたいのかもしれません。村に住んでいる人たちは自分たちの村のことが大好きで、いつもは別々のことをしているのですが、たとえばある家が壊れたら、隣の家に住んでいる大工さんに直してもらって、おいしい野菜をつくっているおばちゃんから野菜のお裾分けをもらって、毎日おいしい野菜が食べられて……といったイメージです。何かそういうそれぞれが得意なことを生かしながら自分らしく人たちが支え合いながら生きているみたいな、組織をつくりたいと思っています。
実際の村だと知り合える人数には限界があると思うんですが、今のSNSなどのテクノロジーを駆使して、人と関わることを技術がサポートすれば、70億人、80億人の村ができるかもしれない。村の子どもがお腹を空かせていたらご飯をあげるじゃないですか。同じように地球の裏側でお腹の空いている子がいたら食べ物をわけてあげる。愛情に飢えている子がいたら、大丈夫だよってすぐ手が差し伸べられる。そんなコミュニティになったらいいなと思っています。
――最近、日本では「イノベーションを起こすためにダイバーシティ(多様性)が重要」みたいなことをよく言われます。このウニ型組織では、そのような効果はあるのでしょうか。
大澤 まだ、モデルでしかないですね。ウニ型組織の理論が「これをしたらこういう成果がある」というレベルには残念ながらまだなっていません。「こうすればこうなる」という理論が確立したというよりは、「こうしたい、こうしてみたらどうだろう」と議論しながら、みんなで一生懸命考えているというのがまだ僕らの段階なのかなと思います。
ウニ型組織という理論を提唱して、それに変えればうまくいきますということではないと思うんですよ。未来のあり方ってこうだから、こういうふうになるためには長い道のりかもしれないけど、ここから順番に変えていこうみたいな、そう逆算しながら設計していく必要があると思います。未来のことを僕なりに一生懸命考えてつくった組織ですね。そうやって長い目で、1個ずつ確実に未来を創造していかなきゃいけないのかなと思います。

「1個ずつ確実に未来を創造していくことを続けていきたい」
ドラえもんをつくるプロジェクトは第2クォーターに
――大澤先生の研究の最終目標は、ドラえもんをつくることですが、ここ数年の目標みたいなことはありますか。
大澤 2014年の秋頃に、僕は「全脳アーキテクチャ若手の会」を立ち上げたんですが、そのときに「30年後に来る、AIとともにいる未来をこの仲間たちと描きたい、30年続くような組織をつくりたい」と言って、立ち上げたんです。だから、2044年頃にはドラえもんをつくるという一大プロジェクトに区切りをつけたいと思っています。2022年3月で、ちょうど7年半ぐらい経ちました。だから、第1クォーターが終わったみたいな感じなんです。30年後に僕らのプロジェクトが完了するというロードマップでは、ドラえもんを実際に開発することに集中する期間が15年間はほしくて、それまでの2クォーター目は、自分がドラえもんに集中するための地盤固めの期間だと思っています。だから、これからの7年半に僕は大学の中で新しい価値創出のあり方や新しい組織のあり方をつくることをやりきらなければいけないと思っているんです。
そのためには、RINGSという組織をもっと温かくて、もっと盛り上がって、もっと人が集まってきて、パワーがみなぎっていくみたいな、そんな組織に仕上げていくことが必要だろうと思います。その上で、残りの15年間を走りきるロードマップは、もう考え尽くしてあって、あとは手を動かすだけにしておきたい。そこまでに、「こうやったらできるぞ」っていうドラえもんの完成イメージをしっかりつくり込みたい。なので、これからの7年半でもう準備は完璧という状況にしたいですね。

作成中のロボットと大澤先生。ミニドラのようなロボットは「ドラドラ」や「ドララ」としか話せないが、それで人間とコミュニケーションが取れる。
<「著名人インタビュー「あの人のスマートワークが知りたい!」」 前回リンクと次回予告 >