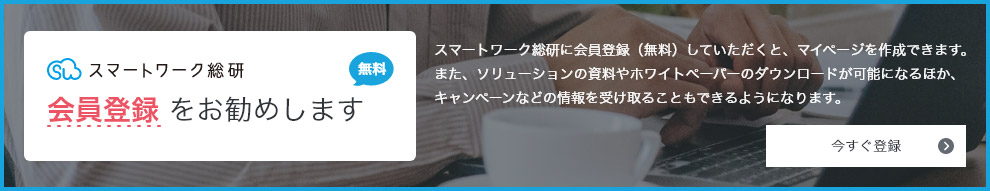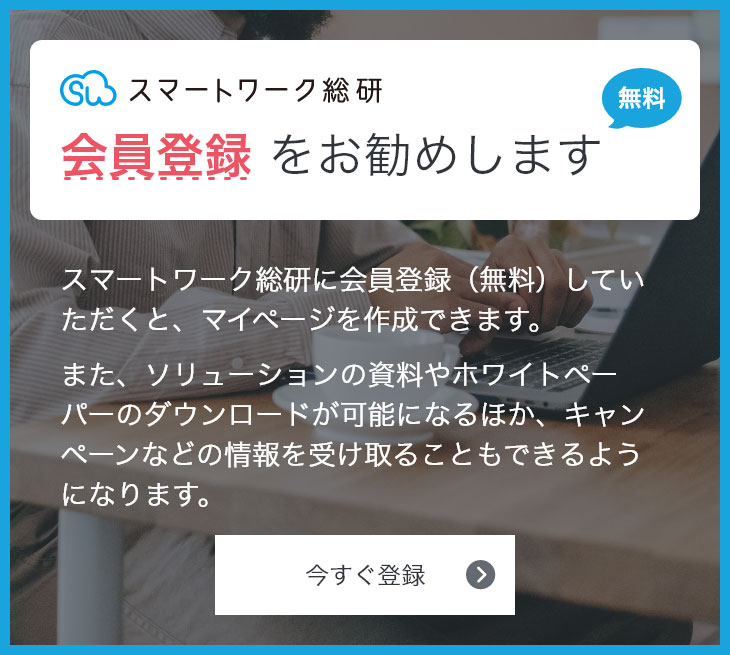ウィズコロナの働き方はどう変わるのか?
~オンラインセミナー報告

新型コロナウイルスの影響により、リアルで催されていたセミナーや講演会の多くはオンラインに移行した。オンラインセミナーは様々なテーマで開催されているが、今回はコロナ以降をにらんだ「働き方」についてのオンライン勉強会の内容を紹介する。
文/狐塚淳
在宅テレワークの孤独を取り除くには
2020年5月20日、「緊急事態宣言で企業はどう変わったのか? afterコロナ、withコロナの“働き方”を紐解く」と題されたオンライン勉強会(主催:株式会社OKAN)が開催された。緊急事態宣言により各種店舗の休業要請や不要不急の外出の自粛要請が出されたが、解除後もウイルスが無くなるわけではなく、「新しい生活様式」の採用が求められるようになる。しかし、まだその実態は明らかではない。
今回の勉強会では様々な業態の4社が、現状の分析や取り組みをもとに、ニューノーマル時代の働き方状況を考えるセッションを行った。Zoomウェビナーを使用したため、オーディエンス側からは、他の参加者の姿は見えず、主催者側とのやり取りは、セッション後のQ&Aとチャットに限定されていた。リアルのセミナーに比べて寂しい感じもなくはないが、聞き手は自宅などからアクセスできるため、セッションの視聴に集中できる。
最初のパネリストはサイボウズのコーポレートブランディング部長である大槻幸夫氏。「なぜテレワークは定着が難しいのか?」をテーマに講演した。長くグループウェアなどを提供してきた同社では、現在Excelなどのデータから簡単にアプリを作成できるキントーンに注力しており、最近では大阪府のコロナ対応の病床数を知らせるアプリがキントーンを利用して作られ、別の自治体でも利用されるなどの成果を上げている。
現在、働き方改革の先端企業として評価されている同社では、2010年8月からテレワークの試験導入を開始した。しかし、当初、テレワークをする場合前日に届け出なくてはいけないなど利用の条件が厳しくなかなか定着しなかった。だが、その翌年東日本大震災発生後に、規則を緩和して強制導入を開始たことで、すでに機器なども用意できていたために、利用が増大した。
大槻氏はテレワークを定着させるには「制度」「ツール」「風土」の3つを用意する必要があると説明した。「(人事)制度」と「(IT)ツール」はどの企業でも考えるが、「風土」というのは「みんな何をしているのだろう?」というテレワークで発生する不安のケアを可能にする環境のことだという。
サイボウズでは、グループウェアで個々の仕事などが見える形を進めることで、不安を解消した。オフィスをクラウド上に再現することで、在宅勤務時にも従業員同士の可視化を高める、会社の様子がわかる「オープンチームワーク」という戦略をとった。
そこで重要になるのが情報共有の方式だ。使用するツールによって風土が決定される。メールベースだと宛先のグルーピングが組織の壁を生むが、情報の仕切りをなくしオープンにシェアすることで、別セクションのやりとりも見えるようになり、効率的な社内コミュニケーションを実現し、通知は来ないが情報を見に行くことができる。「情報共有にとどまらず、状況共有が可能になる」ことが必要だと大槻氏は指摘する。
普段からデジタルオフィスの中でのコミュニケーションが可能だから、会社の動きがわかり、従業員は自宅で働いていても孤独を感じず、不安にならずに仕事をすることができる。クラウド上に、隣で働いている人間を実感できないと、コロナ後に元の働き方に戻っていってしまう可能性が高いのではないかという。みんなが同じ場所にいるクラウド上のインフラを作り、そこから制度・風土を構築していくのが望ましいと語った。
コロナ後の採用戦略はどうなるのか?
次のパネリストはパーソナルキャリアdoda編集長の大浦征也氏。一般には新型コロナによって多くの企業活動が停滞して不景気になり、大量の失業者が生まれることも予想されているが、大浦氏は、新型コロナ流行以前からの採用データを元に、「コロナで変わる採用状況と今後」というテーマで講演した。
大浦氏は求人状況の変化のグラフを見せて、コロナの影響を説明した。数か月前には40数年ぶりの活況を呈していた求人マーケット。3月4月は下降局面になったが、リーマンショック後ほどではない。有効求人数は3月に10%以上、4月には30%水準で減少した。求人減少は特に宿泊業や飲食業で大きいが、まんべんなく他業界に広がっている。
現在は転職を恒常的に意識している人も多いため、求職者数は107%ほどある。このため、4月は募集している企業には応募が増えている。4月の企業アンケートでは、募集への影響は半数程度だったが緊急事態宣言以降は増加すると思われる。このため、人材採用投資が可能な企業にとっては、優秀な人材を集めやすい状況になっている。
採用手法も変化してきている。採用を続ける企業でも、採用活動は全面オンラインに切り替わり、採用プランの再考が必要になっている。現在はプロセス的に最終面接の手前で足踏みしている企業ばかりだという。
今後、採用・転職における変化としては、応募者側からは、テレワークなどが可能かといった働き方の自由度や、経験を活かせるかなどが応募条件で重きを置かれるようになってきている。今回の対応をもってする企業のテレワークなどへのスタンスが、採用状況にも影響を与えそうだ、従業員の人生に配慮しているという企業ブランド自体が採用競争力に影響を与えるのではないかと語った。
ワークライフブレンドが進む
続いて登場したのはキャスター代表取締役の中川祥太氏。同社は企業の仕事を在宅でサポートするオンラインアシスタントを紹介する「CASTER BIZ」事業を展開している。700名のスタッフがフルリモートで働くキャスターの本社事務所は宮崎県の酒造の二階にあり、賃料は月に数万円で、会社自体もほぼバーチャルだという。もともとはオフィスを持たない、オンラインコミュニケーションだった。社内のオンラインイベントも多く、今回の自粛で一気に広がったオンライン飲み会も、同社では5年くらいやっているという。
同社が企業に紹介するオンラインアシスタントで、子供がいるのは3割程度。働き方に制限があってリモートワークするのではなく、リモートワークという働き方を選択しているケースが多数派だ。
企業のオンラインアシスタント採用は、企業継続のために人材採用が厳しくなった2年くらい前から増加してきている。
現在、国内のリモートワークの採用は27%、3割弱というところだが、都市部では第三次産業従事者が7割あり、店舗などではその場にいないと働けないため、すでにかなりの普及率だと感じているという。
キャスターの働き方はオフィスレス、通勤レス、ボーダーレスだが、これを加速していくには、スタッフはワークライフバランスからワークライフブレンドという切り替えを考えていかなくてはならない。単に仕事とオフィスを家に持ち込むだけではいけない。家はオフィスではないため、たとえば1LDKで夫婦がいて子供が生まれた場合、両者がリモートワークで子供を預けられないとすると在宅の勤務環境は厳しい。
会社には椅子やPC、セキュリティなどが揃っている。生活にオフィスを持ち込むのではなく、仕事自体を変えていき、生活にブレンドしていくことが大切になる。書斎のような住環境がない場合、そういった空間にオフィスの当たり前を持ち込んでマネジメントを考えるより、仕事を変えて生活のなかにブレンドしていく、個人の選択肢で仕事の家への持ち込み方を選べるようにすべきだと考えていると述べた。
同社のサイトでは、そうした働き方の参考になる「働き方図鑑」を公開している。
福利厚生の舞台が家庭になる?
最後のスピーカーはOKAN代表取締役CEO 沢木恵太氏。同社は法人向けぷち社食サービスの「オフィスOKAN」や組織改善サービス「ハイジ」を提供している。
そうしたビジネス経験をもとに、ウィズコロナ時代の福利厚生のあり方を解説した。日本に長く根付いている福利厚生・従業員支援がコロナによる社会トレンドの変化によって、どう変わっていくのか?
人口減少と高齢化によって、日本では求人倍率が上がり採用難に陥っている。企業継続のためには人材の定着(リテンションマネジメント)が必要だ。既存従業員の定着を重視するなら、仕事へのやりがい(モチベーター)だけではなく、離職理由の8割近くを占めるハイジーンファクター(衛生要因)に注目しなくてはならない。
そのためのひとつのファクターである、企業が福利厚生のために使う法定外福利費は国内で年に17兆円規模になる。従来型の保養所などの福利厚生を見直し、育児支援や健康管理にフォーカスした福利の増強に組みなおすことが必要とされている。
沢木氏は、テレワーク時代の福利厚生・従業員投資の方法として自宅での企業の仕事を支援する「企業仕送り」が重要ではないかと提案した。コロナによって自宅消費が増加している現在、企業の福利厚生も、親から学生への仕送りのような形が必要になる。仕送りは生活を補助するお金やモノだ。
仕送りは使用用途を詳細に明確化することなく支援することが重要だ。企業の福利厚生でもまだライフライン支援はないが今後は変化していくだろう。そこでは物を送ることもありうる。自粛下では「オフィスOKAN」を自宅で使いたいというニーズも伸びているためぷち社食をオフィスから家庭へ送り先を変更する「オフィスOKAN仕送り便」を開始した。
「ハイジ」のユーザーデータでは、テレワークで企業のハイジーンファクターは一時的に悪化したことがわかった。しかし、新しい福利厚生の形をアレンジしていくことで、改善が可能なはずだ。
コロナウイルスによるテレワークで大打撃を受けた、医療や交通、物流などはその場に行かないと仕事ができない。こうしたダブルスタンダードは続くだろうが、これからは、テレワーク企業にも、特定の場を必要とする企業にも、今後は従来の福利厚生投資とは異なるアプローチが必要とされている。
新型コロナウイルスがあぶりだしたビジネス課題
新型コロナウイルスの流行による緊急事態宣言は、多くの企業にとって、仕事のスタイルや内容を見直す機会になった。リモートワークが推奨される中、自社の業務のうちどのくらいが在宅勤務などで処理が可能であり、そこでどんな生産性が実現できるかを、皆が模索した。
今回のオンラインセミナーは、テレワークツール提供、人材募集、リモートアシスタント提供、福利厚生と、さまざまな業種の立場から現状と今後の予測が解説された。そこで、見えてきたのは新型コロナウイルスの流行が浮き彫りにした働き方の課題の多くは、従来から企業が抱えていたもので、今回の事態で、時代変化への対応を急がされただけのものが多いということだ。
今回のセミナーは、これらの課題の解決に向けていかに考察し、どんなアプローチが可能かを探るヒントになったのではないだろうか?

筆者プロフィール:狐塚淳
スマートワーク総研編集長。コンピュータ系出版社の雑誌・書籍編集長を経て、フリーランスに。インプレス等の雑誌記事を執筆しながら、キャリア系の週刊メールマガジン編集、外資ベンダーのプレスリリース作成、ホワイトペーパーやオウンドメディアなど幅広くICT系のコンテンツ作成に携わる。現在の中心テーマは、スマートワーク、AI、ロボティクス、IoT、クラウド、データセンターなど。