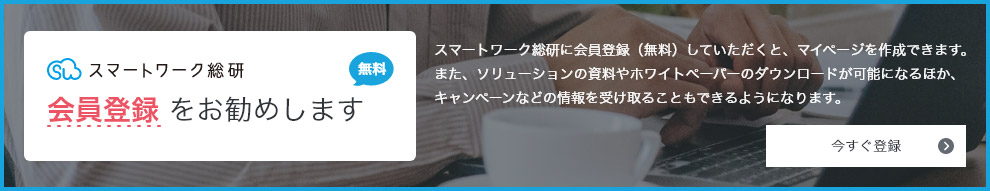あの人のスマートワークが知りたい! - 第29回
電子書籍の新しい文化を作りたい
~株式会社ボイジャー社長 鎌田純子さんに聞いた
電子書籍のパイオニアとして1990年代から電子書籍の普及に努めてきた株式会社ボイジャー。出版不況と言われる中でも、近年の電子書籍市場は拡大。2020年度の電子書籍の市場規模は4821億円と推計されており、2019年度の3750億円から28.6%も増加している。電子書籍の過去とこれからについて社長の鎌田純子さんに聞いた。
文/豊岡昭彦

鎌田純子
株式会社ボイジャー代表取締役社長。1957年、神奈川県生まれ。北海道大学薬学部卒。1981年、レーザーディスク株式会社(後のパイオニアLDC)入社。レーザーディスクの市場導入やマルチメディア作品の企画・制作に従事した後、1992年、株式会社ボイジャーの設立に参加。CD-ROMやWebのプロデュース、電子出版関連ツールの制作・販売などを担当。『マニフェスト 本の未来』日本語版チーフエディターでもある。2013年より現職。
https://www.voyager.co.jp/
電子書籍とは何か
――日本の電子書籍のパイオニアと言われるボイジャーですが、1990年代から電子書籍の普及に努めてこられました。電子書籍とは何なのかを説明するために、ボイジャーの歴史をふり返りながらご説明いただけますか。
鎌田 株式会社ボイジャーを1992年に設立して、最初に出した製品は、共同設立者だった米国のVoyager社が開発した『Expanded Book Toolkit』という電子書籍を作るソフトウェアでした。Macintosh用のソフトで、これで作った電子書籍をMacintoshで読むというものでした。アップルコンピュータ(現アップル)がPowerBookというポータブルコンピュータを出したときに、Voyager社のスタッフがその液晶画面に表示されている文字を見て、「まるで本みたいじゃないか」と思ったことから生まれたものです。ハイパーカード(HyperCard)というアップルコンピュータ社のオーサリングソフトで作られたものでした。
この『Expanded Book Toolkit』を使って、アメリカのVoyager社が最初に出版したのが後に映画化もされたマイケル・クライトンの『ジュラシックパーク』という小説で、フロッピーディスクで提供されていました。マイケル・クライトンはMacintoshで、Palatinoというフォントを使って小説を書いていたんですね。読者は著者が書いた原稿と同じ状態のものを読むことができるという趣向です。
日本では、パソコンの展示会に出展すると「すごいね」とは言ってもらえるのですが、その次には「Windowsでは動かないんですか」、それから「縦書きはできないんですか」という質問が来るわけです。私たちは、Windows よりもMacintoshのほうが魅力があると信じていたし、そのうちにMacintoshがWindowsを凌駕するくらいに思っていたので、当時はWindowsパソコンで読むことにそれほど真剣ではなかったんですね。
その後、Windowsでも読めるようにしようと考えるきっかけになったのが1995年に発売した新潮社と共同開発の『CD-ROM版新潮文庫の100冊』という製品です。CD-ROMに新潮文庫100冊分の作品が入っているものですが、塩野七生さんの『コンスタンティノープルの陥落』とか、最近まで電子化が許されなかった作家の作品も収録されているという画期的なものでした。当時、価格が1万5000円もしたんです。でも100冊入っているから、1冊150円なので、文庫で買うより安いじゃないかみたいなのりでした。
新潮社といっしょにこれを制作するときに、課題となったのは、Windowsでも動くことはもちろん、縦書きができること、ルビが振れること。それから文字がMacintoshのフォントではだめで、大日本印刷が権利を持っている秀英体という書体を使うこと。さらに、「シフトJIS」で一般的に使われているような「新字」だと、読んだ気がしないので、活字と同じ「正字」で表示されなければいけないことでした。それで、秀英体の明朝体で、新字と正字の書体を提供してもらい、それをボイジャーが作った表示システムの中でコントロールできるようにしたんです。だからシフトJISではあるけれども、「冒涜(ぼうとく)」が「冒瀆」と正しく表示できるし、森鷗外の「鷗」も正しく表示できるようになりました。このときに、ボイジャーは、本としての基本的な作法を学んだわけです。
いろいろな出版社に共同開発を持ちかけましたが、「電子の本をいっしょに出しましょう」と、本気で言ってくれた出版社は新潮社が初めてだったんです。いまあげたようなさまざまな課題はありましたが、それをクリアしたら出しますと言ってくれました。それで、一生懸命にソフトウェアを作って、発売までこぎ着けました。結果的に、1万5000円もする電子書籍が3万部も売れました。1995年当時、4億円以上の市場があったということです。私たちはすごく喜んで、世界が変わるかもしれない、他社も追随するだろうと思いましたが、実際には誰もついて来ませんでした。やっぱり当時の電子書籍に何かが足りなかったのだと思います。
そしてちょうど同じ時期に、電子書籍の歴史にとって重要な出会いがありました。ある展示会で、富田倫生さんという方がボイジャーのブースに相談に来られました。自分がインターネットを通じて情報を調べ、苦労して書いた著書『パソコン創世記』が絶版になってしまうので、それを電子版にしたいと。それから、世話になったインターネットにも貢献したいと。そうした流れで、1997年に富田さんほか数名で始めたのが著作権の切れた作品を電子化してストックする「青空文庫」なんですね。ボイジャーは、青空文庫にサーバーを提供して立ち上げに協力しました(その後、移転)。
――青空文庫は、無料で本が読めるわけですから、パッケージとして電子の本を販売したいという出版社やボイジャーの意向とは反するものではなかったのでしょうか。
鎌田 青空文庫は、電子書籍が社会的に認識されるという意味では、必要なものだったと思います。ボイジャーは、フロッピーやCD-ROMのパッケージを販売していましたが、1995年にWindows 95が発売されて、インターネットの波がやってきました。インターネットが持っている、今までにない革命的な力に、どう向き合ったらいいのかを考えました。まだブログはなかったですが、ネットの日記が流行っていて、毎日更新している人が出始めていました。青空文庫にも徐々にデジタルテキストがたまり始めていたし、我々はそうしたものをもっと読みやすくできないかと考えました。
そこで、インターネットで本を読むソフトを作ってみることにしました。当時のインターネットのブラウザはまだ貧弱で、ワープロがそのまま画面に出ているようなものでしたから。日本語で読むのだから縦書きで、文字詰めやフォントなども考慮し、きれいに整えて、本を読んでいるように読めるものを作りました。T-Timeというアプリケーションで、開発コンセプトに合わせて「Hi-Fiテキストリーダー」と呼んでいました。
Hi-Fiテキストリーダーには、大きな問題があって、誰でもわかると思うのですが、インターネットで見るテキストは無料ですよね。買うものではない。だから、ネット上のテキストを読みやすくしても出版社としてはビジネスにならない。そこで、著作権管理ができるように「ドットブック(.book)」というT-Time専用のファイル形式を開発しました。
ドットブックを開発しているときに、実は出版業界も大きい変化を迎えていたんです。出版需要が1996年にピークを迎え、それ以降現在に至るまで右肩下がりになって、シュリンクしていくんです。
このままでは危ないと思った大手出版社8社が集まって2000年に始めたのが、「電子文庫パブリ」というインターネット電子書店です。ただ、それぞれの会社が別々のフォーマットで電子書籍を販売していて、PDF、ドットブック、XMDF、テキストデータなど各社バラバラのファイル形式で販売されていました。電子書籍の販売サイトとして、1つにまとまってはいましたが、読者にとってはあまりありがたくない仕組みですよね。
そして、ちょうど同じ頃に、携帯電話で読む漫画のブームが来ました。漫画を出版する会社が競争するにしたがって、携帯電話という小さい画面の中で、フォーマットがどんどん増えていきました。この漫画を読むにはこのアプリ、あの漫画を読むのは別のアプリが必要という状態になっていました。
この電子文庫パブリと携帯電話の漫画の動きを見て、我々が決断したのは、ドットブックをやめようということでした。ボイジャーがドットブックという固有のファイル形式にこだわると、1つの本をいろいろな書店で売るとか、その本を後世に残していくということができないからです。紙の本は、100年前のものでも誰でも開いて読むことができます。ところが独自フォーマットのデジタルデータは、それのリーダーが使われなくなったら読むことができなくなります。我々はこれを創業当時にリリースした作品で経験しました。アップルのハイパーカードで動いていた電子書籍は、ハイパーカードがサポートされなくなると、まったく読めなくなりました。本としては、後世に残せないのは致命的な欠陥です。ですから我々は、ドットブックをやめて、国際電子出版フォーラムが制定した標準フォーマットePubに切り替えようと考えました。標準フォーマットなら、長く残すことができるからです。2010年ぐらいに、それまでのビジネスを捨てて、ブラウザベースで標準フォーマットであるePubを表示するための読書システムを作って、それをライセンスしてビジネスにできないかということを模索し始めるんです。
そして、2011年に発表したのが「BinB(ビーインビー)」という読書システムです。Books in Browsersの略称です。電子書籍で世界標準となっているePubのほかに、PDFなどさまざまなフォーマットに対応しています。BinBは、もちろん縦書きができて、絵や文字も読めるけれども、コピーや印刷はできないし、出版社の作品であればちゃんと購入した人しか読めないようになっているので、著作権は守られます。これが2013年ぐらいからだんだん芽が出始めて、いままで続いているという感じです。
――BinBという読書システムでは、読者はBinBというシステムを意識しないで読めますよね。出版社はBinB特有のライセンスを付与して電子書籍データを作っているんですか。
鎌田 読者は、特別なソフトウェアを使わず、一般的なブラウザでそのまま読めるので、読書システムを意識しません。「読む」というボタンを押したら読めるのが特徴です。読者にBinBで本を読むというライセンスを付与するのは書店がやるので、出版社はやりません。出版社はできるだけ長続きするフォーマットで作りたいと思っているし、ビジネスの形態としてはストックのビジネスですから、出版社はどこででも売れる、いつまでも売れるものを求めています。大きい出版社ほど電子書籍で痛い目に遭っているので、将来なくなってしまうかもしれないフォーマットに対して非常に強い警戒感を抱いています。
出版社は、ePubやPDF、漫画だったらJPEGといった一般的なフォーマットで作品を作るだけでいいんです。BinBを採用している書店では、それを受け取ったら、BinB形式にデータを整えて棚(Webサイト)に並べる。棚に並んだ本を読者が見て、買って読むということになります。
捜し物は何ですか
――ボイジャーが1990年代に出した電子書籍は、ビートルズの映画を1本全部入れるとか、あるいは詩の朗読のムービーとテキストをリンクさせるとか、紙の本ではできないことができる、まさにExpanded Book(拡張した本)というイメージでした。それがテキストに収斂したのはどうしてなのですか。
鎌田 私にとって電子書籍というのはやはり本なんです。紙の本を作っている出版業界の人たちは、紙の本と電子書籍を区別しますが、私にとっては区別がないんです。電子書籍はまず本でなければならない。ページをめくって文字が読めて、100年後にも残ってちゃんと読めなければならない。ただ、本ではあるけれども、電子だから電子の良さがくっついている本でありたい。e-bookのeは何でもできるという意味ではなくて、電子の良さがbookにくっついているというものでありたいのです。
初期の電子書籍は確かに、CD-ROMに入っていて、映像や音声が付いたものでした。それはパッケージのビジネスだったからで、今はインターネットの時代なので、インターネット上にある映像や音楽をテキストにリンクするのは簡単です。でも、それに魅力を感じるかというと、それほどでもないですよね。CD-ROMの時代は閉じられた世界だったから、それに魅力を感じたけれども、インターネットの世界では映像も音楽も溢れているから、それが本にリンクしても、大きな魅力ではありません。
本にeがくっついたときに、私がもっとも重要だと思うのは「検索」です。「捜し物は何ですか」ですよ。捜し物は不思議で、私が社会人になってだいぶ経つのですが、仕事の9割が捜し物です。あれはどこに行った、これはどうした、いつやったかと。要するに捜し物なんです。その捜し物を助けてくれるのがデジタルではないか。デジタルが便利だと感じるのは、捜し物が一瞬でできたときです。Googleなどのインターネット検索もそうですよね。だから、電子の世界がテキストに寄っていく一番大きい要素は、検索ができるということだと思います。そうじゃなければ、図書館にある本のほうがよっぽど多いし、いいわけですが、図書館の本は内容までは検索できない。でも、電子書籍ならできます。
検索はなかなか難しいんです。たとえば、ボイジャーは今、スポーツ専門の出版社さんと仕事をしているのですが、検索するとなると、「読売ジャイアンツ」なんていうものを検索したらものすごい数の雑誌や記事がでてきてしまう。さらに、「読売ジャイアンツ」だけでなく、「巨人」でも「巨人軍」でもヒットしなければいけないし、検索したい人が求めている記事に瞬時にたどり着くにはどうすればいいかという工夫が必要です。紙の本では、それを編集者が目次やタイトル、見出し、ビジュアルなどで補っているわけです。それはまだ残っていくものだろうと思いますが、とにかく電子の世界では検索ができないといけない。そのために、OSや環境、ソフトウェアに左右されやすい映像や音楽はリンクで済ませることにして、まずは本の中身を検索してナビゲーションできること。そのためには、テキストだということです。
――電子書籍では、漫画は売れていますが、それ以外の作品はあまり売れていないと思います。漫画以外の電子書籍を普及させるのに必要なことは何ですか。
鎌田 世の中の人が目を向けてくれるために、最も重要なのは「慣れ」なんです。スマホを持っていると、それで文字を読んだりすることに慣れてくるじゃないですか。漫画もそうです。2020年度の出版業界全体の市場規模が約1兆6000億円、電子書籍の市場規模が約4800億円くらいの中で、電子書籍の漫画が4000億円(電子書籍市場のシェア83.0%)もあるのですが、漫画は無料で読まれている部分が大きいわけです。多くの若者は、1日1話なら無料で読めるサービスを利用して、漫画を読んでいます。電子書籍を読んでいるという感覚がないけど読んでいる。これが慣れですね。たとえば、買い物もウェブサイトでクレジットカードの番号を入れることに対してだんだん慣れてくる。慣れてくると、人間は簡単で便利というものに抵抗できないんです。おそらくここから先、電子書籍に慣れる人がどんどん増えてくると思うんですけど、慣れてくれば漫画に限らず、電子書籍で読むことに抵抗がなくなってくると思います。
今、小中学校の国語の教育でもICT を取り入れなければならないという中で、電子書籍を作るシステムを提供したりしているので、こうした活動が進んで行けばもうすぐみんなが慣れるのではないかと思っています。
ボイジャーは電子出版社なのか?
――一般に電子書籍の会社というと、コンテンツを作る、いわゆる出版社というイメージです。ボイジャーもコンテンツを出していますが、今のお話を聞くと出版がメインではないようですね。
鎌田 最初はボイジャーも、出版社のようにコンテンツ制作が中心でしたが、今は自分たちが出したいと思う本だけを出すようにしています。年に2冊やれればいいぐらいのことで、出版社としては超零細、いわゆる個人出版に近いと思います。出版という意味では、作家の片岡義男さんの全著作をデジタル化するプロジェクトも進めています。現在、1677作品が電子化されていて、会費制で運営しています。会費を払ってくださる読者の方はすごく熱心なのですが、利益はまだ出ていません。1人の作家のコンテンツを1カ所に集約するとどんなことが起こるのかを試す、ある種の実験としてやっているわけです。昨年は片岡義男さんの小説449作品のデータを、国立国会図書館に納本したんですが、これも画期的なことだと思います。
私は、人に読ませるために書く、人にわかってほしいから書くという行為はとても大事なことだと思うんです。自分勝手に並べ立てるのではなくて、わかりやすいように順番に並べようとか、論理的に書こうとか。もちろん自分が楽しいから、書きたいから書くのですが、誰かに読んでほしいから文章を書くのは、音楽とか写真とか、そういうのもすべてそうだと思うのですが、その姿勢が人生を良くしてくれるような気がするんです。その気持ちがあればどんなものでも本にできる。それがなければ本ではないと思います。本はやっぱりパブリッシュするものだから、人が読むということを前提にしなければ出す必要がないというか。
これはアメリカ人のジョン・オークスさんという人に教えてもらったことですが、出版社publisherと著者の関係をカウンターパート(対等な関係)だと言うんですよね。publisherとして重要なことは、著者が書いた意見を信じることができて、それを読者に届けるための役割を果たす。著者に足りない部分を補って、カウンターパートとして振る舞うものがpublisherだと彼は言うんですよ。理想論ですが、その形で著者が出版人を介して読者と向き合えると、ヘイトスピーチのような、人種差別や個人攻撃のような本も減ると思うんです。本を書くということそのものに、そういう浄化機能みたいなものがあるような気がするんです。
――デジタル出版ツールRomancerですが、個人使用では無料で公開されていますが、有料のものもあるのですか。
鎌田 Romancerは業務用というのがあって、これは売り物ものです。たとえば出版社が使う場合は、お金をいただきます。機能は似たり寄ったりですが、それはそうですよね。一般の人が一生に書く本は多くても数冊ですから、無料でもいいですが、業務用で利用する人は毎月何冊も作っていくわけです。あと数年経つと、新刊書籍と同時に電子書籍を用意してくださいというのがあたり前になると思いますが、編集が終わって校了したデジタルテキストをどうやったらうまく抜き出せるかもノウハウなんです。DTPソフトからきれいにePubを作りたいなら、ぜひボイジャーに頼んでいただきたい。
実は、ボイジャーが現在開発中の最新の電子書籍制作ツールで「NRエディター」というものがあるのですが、誰でも簡単に電子書籍が作れます。「新規作成」を押して、テキストを読み込んで、タイトルや小見出しを指定すれば、あとは表紙や目次、奥付を自動的に付けてくれて、電子書籍ができるんです。写真を貼り込んでキャプションを付けることもできます。それを保存して、変換を押したら、ePubのデータができて、同時にBinB化されて、URLができます。BinBのURLがあれば、その電子書籍を読むのは簡単です。これはボイジャーのRomancerのサイト内の「NRエディター」というコーナーでベータ版を無料で一般公開しています。Romancerも電子出版のツールですが、それをさらに簡略にしたRomancer専用エディターがNRエディターです。さきほど言った小中学校の国語のICT化に向けてもこれを提供しようと思っています。
――クラス文集を簡単に作れますね。
鎌田 そうです。学年分、全部入れても大丈夫です。デジタルだから、閲覧の権利をコントロールするのも簡単で、そうすると学内だけで見られるとか、家ではIDを持っていれば見られるとか、そのIDも学校を卒業したら使えなくなるとか、そういうこともできます。
ボイジャーが目指す新しい文化の未来
――ボイジャーは、1992年に4人で創立されたわけですが、鎌田さんは社長になる前はどんなことをやってこられたんですか。
鎌田 プロデューサーと制作実務の責任者、それと広報ですね。4人で始めた会社ですから、何でもやらなければいけないので。今は、創業29年で27名の会社になりました。2013年から2代目の社長として、社員からの相談を受け、みんなとオンラインで週2回ぐらい討議して、決定するという流れで仕事をしています。今年の6月から、好きな席に座っていいという、いわゆるフリーアドレス制のオフィスにしました。来なくていい仕事は家でやって、なるべく会社に来なくても大丈夫ですという形にしました。結果として、やっぱり人の気配が恋しいというのがあったり、口に出して説明するほうが良かったりするので、部署を横断する形でテーマを決めて会議をしています。
――これからのボイジャーの進路ですが、どんな会社にしていきたいですか。
鎌田 ボイジャーが電子出版を生業とする会社だというのは変わらないと思います。ただ、電子出版のシステムだけを営業してビジネスになる時代ではないので、読むこと以外に、電子書籍を作ること、残すこと、売ることを総合的にプロデュースして、ボイジャーのシステムを使ってもらいたいと思います。別に儲けるためではなく、先ほど紹介したNRエディターのように簡単そうだから使ってみたいと思ってほしい。それこそ、明治時代にガリ版(謄写版)ができて、日本中の会社や学校で簡易印刷が爆発的に普及したように、NRエディターで日本中の学校が文集を作ったり、個人が自分の意見や思いを発表したり、自叙伝を後世に残したり、そういう個人が簡単に出版できる、そういう文化ができたらいいと思います。だから、古い話で恐縮なんですけど、私の中では(『Expanded Book Toolkit』のベースになった)ハイパーカードを超えるソフトはまだ見たことがない。環境といい、完成度といい、ローンチの仕方といい。ハイパーカードを超えることはできないけれども、ハイパーカードができなかったインターネットの中の新しい文化を作りたいと思います。ボイジャーの次の時代は、そこを目指していきたいと思います。

筆者プロフィール:豊岡昭彦
フリーランスのエディター&ライター。大学卒業後、文具メーカーで商品開発を担当。その後、出版社勤務を経て、フリーランスに。ITやデジタル関係の記事のほか、ビジネス系の雑誌などで企業取材、インタビュー取材などを行っている。
<「著名人インタビュー「あの人のスマートワークが知りたい!」」 前回リンクと次回予告 >