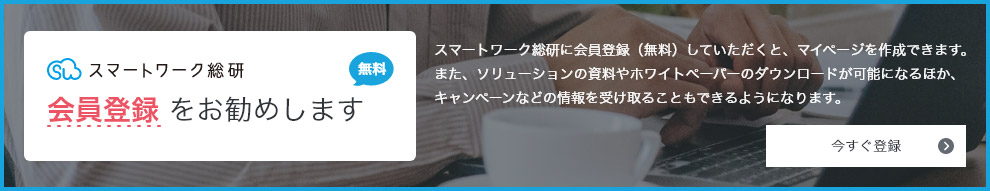鍵は「半径5キロ圏内の問題解決」にある
アメリカを本拠とするGAMAM(グーグル、アマゾン、メタ、アップル、マイクロソフト)、中国を本拠とするBAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)などIT系超巨大企業がIT分野のみならず、商流、物流、コンテンツなど私たちのさまざまな分野で支配的に振る舞うハイパーグローバリズムの時代が到来して久しい。時価総額トップ企業の上位はこれらIT企業が占めており、かつて上位に名前を連ねていたNTT、トヨタなど日本企業は見る影もない。GDP(国内総生産)は中国に抜かれて世界3位だが、今年には4位のドイツに抜かれると予想され、5位のインドにも激しく追われている状況だ。スイスの国際経営開発研究所が発表した世界各国のデジタル競争力ランキングでは、日本は29位でシンガポール、韓国、中国、台湾、マレーシアの後塵を拝している。
そこで著者の坂田氏が日本が再生するために必要だと主張するのが「DXによる半径5キロ圏内の問題解決」。お手本は東南アジアのデジタル・フロンティアだという。
インドネシアにおける「半径5キロ圏内の問題解決」はバイクタクシーのデジタル化から始まったという。同国のユニコーン企業であるゴジェックはスマホでバイクタクシーを呼び出せるサービスからスタートした。
東南アジアの多くの国では、バイクタクシーが庶民の足となっている。オートバイのタンデムシートに乗客を乗せて移動するサービスだ。メーターなど付いておらず、運賃は運転手と直接交渉しなければならない。荷物は背負える程度しか持てないし、事故にあえばケガしたり死亡する率も高い。ぼったくりや強盗まがいの運転手もいる。だが自動車を使ったタクシーより安く、小回りが利くことから重宝されている。
インドネシアの人々がこのバイクタクシーで乗り付ける先は、オートバイで手軽に買い物に行ける距離(半径5キロ圏内)に存在する「パパママショップ」、つまり家族経営の小規模商店だ。日本では旧来の小規模商店がどんどん閉店し、商店街はシャッター街になっているが、東南アジアでは日常消費財市場の大半がパパママショップによって担われている。
人々はパパママショップで買い物をするだけでなく、夜になると店に集まって談笑したりゲームを楽しんでいるという。こうしたパパママショップの仕入れは複雑で非効率的。在庫管理も適当なので商品が品切れになってしまうことも多く、そうすると近くの別のお店に買い出しに行って商品を仕入れてくる。当然価格も上積みされてしまっていた。
ゴジェックが開発したスマホでバイクタクシーを呼び出せるサービスでは、料金は事前に決めるのでぼったくりもない。ドライバーの評価制度を設け、研修・教育制度も作った。さらにゴジェックはヒトだけでなくモノを運ぶサービスを開始し、Eコマースに進出。銀行取引が普及していないインドネシアでも使える新たな決済手段を提供した。
現在はパパママショップの在庫管理や発注をサポートするプレイヤーも登場。パパママショップは多層化しているサプライチェーンを飛ばしてメーカーや一次代理店と直接取引ができるようになり、無駄なコストを削減し、在庫切れも減らすことができるようになった。中間業者という既得権益を打破できたのだ。
DXの本質とは
DX(Digital Transformation、デジタルトランスフォーメーション)という概念が提唱されて20年近くになる(2004年、スウェーデンのウメオ大学 エリック・ストルターマン教授が提唱。日本では2018年頃から普及した)。2022年に経済産業省が発表した『デジタルガバナンス・コード2.0』(旧 DX推進ガイドライン)によれば、DXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」 だというが、この説明ではなんだかよくわからない。
本書では「DXとはデジタル技術を使ってイノベーションを起こすことである。にもかかわらず、多くの企業ではそれがストラテジーやオペレーションのレベルにとどまっている」と言い切る。「オペレーションとはすでにあるものを改善することであり、ストラテジーはやり方を変えること、そしてイノベーションはより大きな変革を起こすことである」なのだ。
インドネシアの例でいえば、ゴジェックがバイクタクシーをスマホアプリで呼び出せるようになったのがオペレーションの変革。銀行取引が普及していない零細店舗を対象に新たな決済手段を提供することでEコマースを実現したのがストラテジー。そしてメーカーと零細店舗を直結し、間に入っていた無数の商社・問屋を介さずに直接商取引ができるように既得権益を打破したのがイノベーションだという。
残念ながら「日本企業の多くのDXと呼ばれるものは、このうちのオペレーションのみにとどまってしまっていることが非常に多い」と指摘している。一方、「デジタル・フロンティアである東南アジアでは、オペレーション改善やストラテジーを実行する手段ではなく、デジタル技術によって社会を変革するイノベーションが生まれているのだ」という。
東南アジアの国々は発展途上国と言われ、確かに公共交通や固定電話回線、銀行などインフラの整備は遅れているかもしれない。そこにも数百年、千年の歴史があり、血脈・人脈で結びついた古い既得権益がしっかり根を張っている。経済発展を優先し、人権を抑圧してきた開発独裁の影が残っているところも多い。既得権益は日本だけの問題ではない。
国際化・グローバル化そしてリージョン化へ
著者は世界の潮流の変化を国際化・グローバル化の時代を経て、現在はリージョン(地域)化の時代が到達しているという。国際化は国境を維持した状態で世界的な貿易が中心となる状態。自動車や家電の輸出入がその代表的存在であり、トヨタやソニーなど日本企業が世界を席巻した。その後に来たのがグローバル化の時代。国境に関係なくボーダーレスにヒト・カネ・モノ・情報がやりとりされた。GAFMAなどITプラットフォームが台頭し、国家に匹敵する力を持つようになった。
2020年代の今、グローバル化が発展する形で進展しているのがリージョン化だという。「全世界共通のサービスではなく、その地域ごとの特性に合わせたサービスを提供し、問題解決を図るというもの」であり、「ヒトが介在する『地上戦』とデジタル技術による『空中戦』の融合がない限り、イノベーションを起こすことはできない」のだ。ここで活躍するのは現地の企業であり、きっかけとなったのがスマホの普及である。
2010年代前半、東南アジア諸国ではまったく普及していなかったインターネットがスマホの普及によって爆発的に一般化し、食事の宅配から医師による遠隔診療までさまざまなサービスがスマホのアプリ経由で受けられるようになった。数年前から中国ではモバイル決済が当たり前となり、屋台や露店でも現金お断り、デジタル決済のみが普通になっているが、近年ではインドネシアなどでも現金での支払いが断られることが多いという。
どうする日本
これまで多くの識者が「アメリカでは」「ヨーロッパでは」「中国では」と他国の先進事例を引き合いに「日本は遅れている」と語ってきた。そこに「東南アジアでは」が加わっても「出羽守(でわのかみ)」(他者の例を引き合いに出して物事を語る人のこと)が増えるだけだ。
本書は東南アジアから日本を俯瞰的に眺め、日本の可能性を述べている。急速に進んでいる少子化は人手不足をもたらしている。人手不足の社会では、テクノロジーの進化によって職を失う人も新しい仕事に就きやすくなる。「現在の少子高齢化という「負」の時代背景は、DXを一気に進めるための「正」の側面を持つ」という。
高齢者にデジタル機器、スマホは使えないというのも思考停止だという。NTTドコモの調査によれば60歳代の9割、70歳代でも7割がスマホを持っている。もちろん持っていることと使いこなしていることは別の話だが、使えない、持っていない人に無理に使わせる必要はなく、周りの人がインターフェースとなってサービスを提供する方法もある。
著者は「DXとは『デジタル技術を使った変革』のことで、必ずしもエンドユーザーが直接デジタル技術を使うことではない」と主張する。さらに日本型組織こそDX化を進めやすいともいう。「日本と東南アジアは既得権益を生み出しているメカニズムや意思決定の特徴でも類似性があり、本書で取り上げた『半径5キロ圏内の問題解決』をするための手法が有効に作用する」のだ。欧米のジョブ型組織によるトップダウンからの変革ではなく、慣習や人脈が幅を利かす非形式制度が残る日本こそボトムアップからの変革が可能となるという。
日本の将来は暗い、と海外へ離脱する人・企業も多いが、誰もが日本を離れられるわけではない。本書は巨大プラットフォームやユニコーン企業を目指すのではなく、「半径5キロ圏内の問題解決」から改革・再生を願っている人にお勧めだ。
まだまだあります! 今月おすすめのビジネスブック
次のビジネスモデル、スマートな働き方、まだ見ぬ最新技術、etc... 今月ぜひとも押さえておきたい「おすすめビジネスブック」をスマートワーク総研がピックアップ!
『アジア新興国マーケティング』(成川哲次 著/幻冬舎)
著者はアジア新興国への進出を目指す企業の支援をするマーケティング会社の代表。以前勤めていたマーケティング会社での経験も含め、長年にわたってアジア新興国の500件を超える市場調査に携わってきました。現地の市場を専門的に分析してきた著者は、アジア新興国と日本とでは商習慣やマーケットの動きが異なるため、現地のリアルな情報に着目したマーケティングを行う必要があるといいます。本書では、著者が実践してきたアジア新興国マーケティングの成功例を挙げながら、それぞれの国の最新事情と調査、分析のノウハウを中心に解説します。リアルな現地情報の重要性とその活かし方を知ることのできる一冊です。(Amazon内容解説より)
『DX戦略の成功メソッド 取り除くべき障壁は何か』(奥村格、武政大貴著/ダイヤモンド社)
チームコンサルティングメソッドにおける現状認識フェーズの必要性を繰り返し説いていく。DX におけるビジョン・戦略策定の重要性を、タナベコンサルティングの戦略フレーム、事例とともに解説!(Amazon内容解説より)
『企業に変革をもたらす DX成功への最強プロセス』(小国幸司 著/幻冬舎)
今やDX(デジタルトランスフォーメーション)は企業経営者にとって最も大きな関心事の一つといっても過言ではありません。DXは、今後企業が生き残るためのキーポイントといえます。DXに取り組んでいる企業が急増する一方で、DXで大きな成果を残し、胸を張って「わが社はDXを達成した」といえる企業は決して多くはないと著者は考えています。こうした企業は、何を目標にDXをすべきか、どのような手段でDXを実行すべきか、DXの成果をどう評価すべきかについて明確な方針と基準をもてていないのです。本書は、著者がこれまでDXに取り組んだ企業の事例をベースに、成功させるために必要な工程やその手法を詳しく解説したものです。業務の効率化、生産性向上を期してDXを検討する経営者、担当者へ向けて、後悔しないDXの手引きとなる一冊です。(Amazon内容解説より)
『DX失敗学 なぜ成果を生まないのか』(佐伯徹 著/日経BP)
DX(デジタルトランスフォーメーション)で失敗している企業は多い。DXに取り組むよう会社から言われたものの、どうしたらいいのか悩んでいたり、取り組みを始めたがうまくいくのか自信がないという人もたくさんいるだろう。筆者はIT関連の開発に長年携わっており、「失敗学」にも多くの経験を持つ。そこから生み出した失敗の真因を究明するためのツール「ITプロジェクト版失敗原因マンダラ図」は関西IBMユーザー研究会で最優秀賞を受賞している。本書ではこのマンダラ図を使って過去のDXプロジェクトの失敗事例を分析し、真因を追究している。構成は、まず、序章でDXプロジェクトの大部分は失敗していることを可視化し、多くの企業においてDXがうまくいっていない現状を伝える。DXを簡易的に確認できるチェックシートを使って、読者自ら現状を把握できるようにしている。(Amazon内容解説より)
<「今読むべき本はコレだ! おすすめビジネスブックレビュー」 前回リンクと次回予告 >