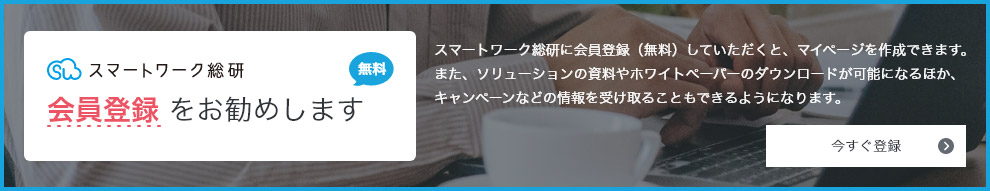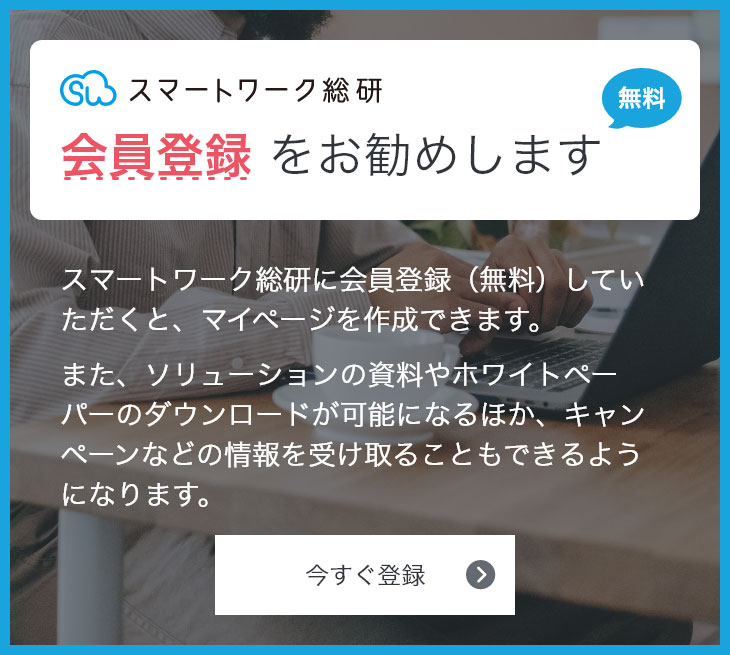売上8割減からの回復
株式会社新規開拓(東京都千代田区、代表取締役社長 朝倉千恵子 正社員17名)は創業の2004年から、会社員向けの研修に力を入れてきた。研修の内容は新入社員や20~30代の育成、リーダーや管理職、役員向けの研修の他に営業・販売力育成、接客・ビジネスマナーに及ぶ。
大きな柱が、ビジネスマナーや心構えを教える新入社員研修だ。毎年3~5月にかけて、主に各企業先で行う。講師(同社の社長、役員、社員若しくは外部委託)が受講生と直接向かい合う、いわゆる対面研修を重視してきた。
4月8日に政府が緊急事態宣言を発令すると、研修の予約をしていた企業から問い合わせが相次ぎ、キャンセルやペンディング(いったん延期)の依頼が増えた。創業以来、初めてだった。
「新入社員研修の3~5月の売上は対年前年同月比で、8割程減になった。社員研修のビジネスに取り組んでいる企業の多くはそれくらいに落ち込んだのではないか、と思う。緊急事態宣言が解除された5月下旬以降、メールやDMで既存のクライアント企業、キャンセルやペンディングで研修ができなくなった企業にアプローチをしてきた。11月現在、元の状態(対前年同月比)に完全には戻っていない。10~11月は、来年3~5月の新入社員研修の契約成立が増え、回復傾向にはある」(専務取締役営業本部長 牧野紀子氏)
いかに講義に厚みを加え、納得感を高めるか
一方、研修の1つである「トップセールスレディ育成塾(TOP SALES LADY 略 TSL)の売上は伸びた。対面研修からZoomを使ったオンライン研修に3月上旬に全面的に切り替えた。受講対象は女性限定。業界や規模を問わず、企業のミドル層が多く、平均年齢は40歳前後。役員や管理職、グループリーダーが半数以上を占める。
研修内容は状況に応じて変えるが、現在は「コミュニケーションスキル」「営業力・稼ぎ力」など。2003年から毎年開催し卒業生は延べ2600名を超える。1クール(約2~3か月間)を8回(1週1日のペースで)開催で、1回は約3時間。計24時間。
管理職研修など他の研修は会社として申し込むケースが多いが、TSLは大半が個人の申し込みだ。1回につき、受講生の平均は約20名。オンライン研修を開始すると、3月以降、申し込みが一気に増えた。4~5月は、60名を超える。その後も増え、9~10月は49名。12月から新たなクールが始まるが、11月上旬時点で申込者含め150名を超える。
「創業以来、アナログ(対面式の営業や研修)で信用と信頼を積み重ねてきた。このうえに、オンラインの特徴を生かした研修を試みたことが功を奏した。まず、地方在住者が受講できるようになったことが大きい。回数を8回(さらにフォローが1回)に増やした。録画を許可し、講義内容を何度でも観ることができるようにもした。値段は回数が増えたために25万円から30万円に上げたが、それに見合った内容にはしている」(取締役マネージャー 阿部由里氏)
企画からパートナー講師との打ち合わせ、講義の運営、受講生のフォローまでを阿部取締役とともに、3名の社員が担当する。4名とも4月以降、基本的にはフルタイム(原則週5日、1日8時間)の在宅勤務だ。出社は、各自1か月平均2~3日程度。3月までほとんどの社員が在宅勤務の経験はなかった。オンライン研修は、週末に講師と社員が秋葉原のスタジオからライブで配信する。ローテーションで社員4名のうちの数人が参加。スタジオ専属のカメラマンや照明、音声担当がいるために、サポートに徹する。4~5月当初は、社員が慣れていないために、撮影の準備がスムーズにできない時があった。この時期に、Zoomの使い方を集中的に練習した。
特に撮影時の講師のポジション(カメラに映る角度)、ボディランゲージ、背景、照明、講師が受講生にする質問の仕方、タイミング、チャットの使い方だ。阿部取締役マネージャーは「いかに講義に厚みを加え、納得感を高めるかに特に力を入れてきた。6~7月頃には概ね滞りなく対応ができるようになった」と話す。
人事のあり方は、もう戻れない
本社の社員(9名)のうち、管理部門(経理、総務、人事、広報)も同じく4名だが、緊急事態宣言解除の5月下旬以降、基本的には現在までほぼフルタイムで出社する。クライアントの企業との契約書や請求書、見積書の文書は郵送でのやりとりが中心となっていたためだ。現在は、双方の話し合いで電子化(ペーパーレス)を進めている。さらに、6月から最近までは社内の事業計画や人事制度改定と重なったためでもある。営業の社員は在宅勤務と出社の併用だが、現在も在宅勤務の場合が多い。
創業期から、社内外の状況に応じてIT化に取り組んできた。当時から全社員に1台ずつパソコンや携帯電話を、最近はスマートフォンを貸与してきた。6月~7月前後からは、社内共有のクラウドシステムにアップロードする社内文書を従来よりも増やしてきた。セキュリティ保護のうえ、一定の制約・制限のもと、自宅で閲覧ができるようにしている。在宅勤務をスムーズにするためだ。
役員や管理職が参加する月1回のリーダーミーティングや全社員参加の月1回の「未来会」も原則としてZoomで実施する。10月の「未来会」は、経営に関する重要なテーマについての話になるために、全員が出社した。来年は、全員が在宅勤務をできるようにすることを検討中だ。
「感染が拡大する前の人事のあり方には、もう戻れないですね。私たちの会社も、世の中も変わることを求められている。オンラインは、これまでは得意な人や好きな人がしていればよかったのかもしれない。今は、誰もができて当たり前になりつつある。この流れについていくために、改革を試みていきたい」(阿部取締役)
リアルが上手くいっているから、オンラインでも上手くいく
営業メンバー7名中5名は、名古屋支店にいる。4月以降から5月下旬までは牧野紀子専務取締役営業本部長のもと、在宅勤務を中心としたリモートワークを徹底させた。6月以降は原則、出社としている。ただし、牧野専務取締役以下、ほぼ全員が名古屋を拠点に出張を繰り返し、動くためにいわゆるデスクワークの時間はもともと少ない。「創業期から各自が会社貸与の小型のパソコンや携帯電話を使い、出先で報告・連絡・相談をしながら仕事をしてきた。全員が出張先からの仕事に慣れていることもあり、4~5月に社内で混乱はなかった」(牧野専務取締役)
4~5月に東京本社・名古屋支店ともに、社員間の情報共有をそれまで以上に徹底させた。一人でいると、心身の健康が不調になるかもしれないことを懸念したという。午後5時半から6時までの約30分はZoomを使い、「オンライン・ワイガヤ・タイム」とした。原則、全員が参加し、1日の仕事の内容や課題、健康面について話し合った。イレギュラーな事務対応の仕事が増えたために共有意識を高め、意思疎通を図るのが狙いでもあった。さらに、1週間に1回は牧野専務取締役と個々の社員が1対1で向かい合い、話し合う「1 on 1(ワン オン ワン)ミーティング」をした。この際は、牧野専務取締役は聞く姿勢に徹したという。
特に力を注いだのは、顧客である企業への対応だ。この期間は、対面の営業ができない。在宅勤務となった企業が多く、電話もできない。そこで「顧客にどのように寄りそうか」に重きを置いた。例えば、「正しい努力を積み重ねる」をコンセプトとして今年初めて自社で制作した「新入社員手帳 Rookie(ルーキー)手帳」を謹呈として、手書きの手紙を添えて郵送した。各自が、日頃の感謝の思いを書く。1社につき、少なくとも便箋で2~3枚。支社の社員全員で 約200社に送った。受け取った企業の役員、担当者からお礼の電話や近況の報告連絡があったという。
顧客の企業へのアプローチも、この時期に変え始めた。従来までは、ほとんどが対面式だったが、メールやZoomを使ったオンライン営業を必要に応じて取り入れるようにした。「現在は、双方を使い分けるハイブリッドにしている。リアルでできること、するべきことはオンラインでも大切。オンラインのビジネスが上手くいく人は、リアルでもよくできているケースが多い。リアルが上手くいっているから、オンラインでも上手くいく」(牧野専務取締役営業本部長)
同社はこの半年で、研修と営業のあり方を大きく変えつつある。現在も在宅勤務を積極的に認め、社内のデジタル化を進める。社員の意識も次第に変わっていくのだろう。2度にわたるオンライン取材の際、牧野専務取締役営業本部長と阿部取締役マネージャーがともに強調したのが、次の言葉だ。「創業以来、アナログ(対面式の営業や研修)で信用と信頼を積み重ねてきた。このうえに、オンラインの特徴を生かした研修を試みたことが功を奏した」。
最近の在宅勤務をはじめ、テレワークに関するマスメディアの報道や風潮、世論は「家で仕事ができるから、働きやすくなった」「通勤がなくなり、肉体的な負担が減った」といった光の面だけを見ている傾向があるように筆者は感じる。だが、ビジネスとはアナログで信用と信頼をつかんでいるからこそ、テレワークは成立するのではないだろうか、とあらためて思う。実は、アナログで信用と信頼を得るのはある意味で苦しく、空しい試みでもある。それでも、挑まなければ信用は得られない。そろそろ、私たちはこういう厳しい現実にも目を向ける時期になっているのではないか。
「コロナに負けない!在宅勤務・成功事例」
記事一覧
-
【1】スマートキャンプ
オンライン夜会で全社員の共有意識を高める -
【2】ツナグ・ソリューションズ
全社員の無期限フルリモート継続決定から矢継ぎ早の大改革 -
【3】株式会社新規開拓
社員研修・人材育成ビジネスを、対面からオンラインへ大改革 ……この記事 -
【4】ピー・アール・エフ
テレワークができるか否かは、「ITスキル」「営業の仕方」で決まる -
【5】株式会社メンバーズ
「240人の新卒者で、退職者たった1人」の在宅勤務 -
【6】ダンクソフト
SmartOfficeと在宅勤務を併用し、常に次の働き方改革にチャレンジ -
【7】トランストラクチャ
オフィス分散化と人事評価の客観化で「出社義務なし」の在宅勤務へ -
【8】Chatwork
オフィス分散化と人事評価の客観化で「出社義務なし」の在宅勤務へ -
【9】東京都豊島区
全国の自治体から問い合わせが相次ぐ、「テレワーク先進区役所」 -
【10】パーソルキャリア
社員が居住地を自由に選べる「フルリモートワーク制度」 -
【11】コニカミノルタジャパン
社内保管文書88%削減を背景に、緊急事態宣言に2か月先行した在宅勤務を実現 - 【12】マクロミル ”社員1000人が出社を前提としない働き方“を着々と、確実に整える

筆者プロフィール:吉田 典史
ジャーナリスト。1967年、岐阜県大垣市生まれ。2006年より、フリー。主に企業などの人事や労務、労働問題を中心に取材、執筆。著書に『悶える職場』(光文社)、『封印された震災死』(世界文化社)、『震災死』(ダイヤモンド社)など多数。